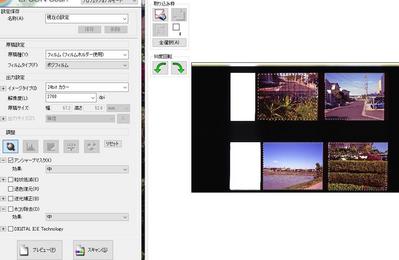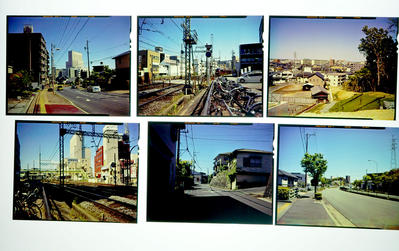���̂a�a�r�ł͋L���V�K���e�y�ѕԐM���̃p�X���[�h�����������Ă��܂��B���L�^�C�g���̉���[�F��]���N���b�N���ăp�X���[�h��
�ucoffee�v�Ɠ��͂��邱�Ƃɂ�菑�����݂��\�ɂȂ�܂��B�Ȃ��A���̋@�\�y�уp�X���[�h�͐����ύX����ꍇ������܂��̂ł��������������B
�y�Q�S���Ԃ̉�L�z
[�g�b�v�ɖ߂�] [���ӎ���] [���[�h����] [�ߋ����O] [�Ǘ��p] [�F��]